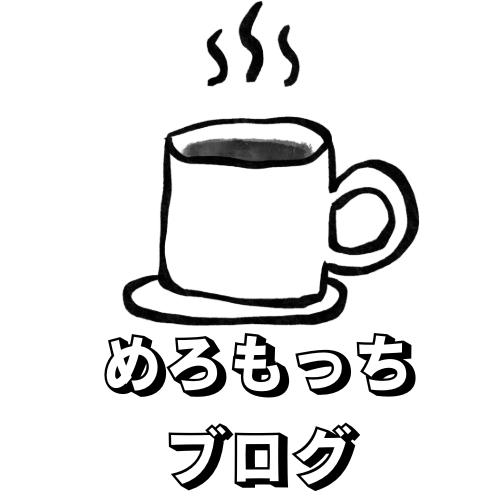認知症と一口に言っても、支援のしやすさは本当に人それぞれです。
症状の程度や環境だけでなく、「その人の生き方」や「もともとの性格」が色濃くあらわれます。
私が現場で感じるのは、大きく2つのタイプがあることです。
「プライドが高く、支援を受け入れにくい人」
「にこにこして周囲から愛される人」
どちらが良い・悪いではありません。
ただ、関わる側の感じ方や支援の進みやすさには違いが出てきます。
ここでは私が実際に関わっているお二人を例にご紹介します。
◆プライドが高く支援を拒みがちなIさん
地域の行事では役員を任されることが多かったIさん。責任感が強く、リーダーとして
周囲をまとめてこられたタイプです。
認知症が進んできた今でもその姿勢は変わらず、「自分でできるから」と
何でも自分でしようとされます。こちらが安全面を考えて手を差し伸べても、
「そんなこと言われなくても分かってる」
「私は人に頼らんでも大丈夫」
と不機嫌になってしまうこともあります。
長年、人に頼らず、役割を担って生きてこられた方だからこそ、
「支援される側」になることをなかなか受け入れられないのだと思います。
こちらも声かけ一つに気をつかう場面が多く、丁寧な距離感が求められます。
◆にこにこ笑顔で愛されるNさん
一方、いつも柔らかい笑顔を浮かべているNさん。もともと幼稚園の先生をされていたそうで、
人と関わることに慣れておられます。
支援に入ると、
「まあ、ありがとう」
「助かるわぁ、悪いねぇ」
と自然に感謝の言葉が返ってきます。何かを拒否したり否定したりすることもありません。
私たち支援者も、その笑顔にこちらが癒やされることさえあります。
同じようにサポートをしていても、こちらの気持ちの余裕や安心感がまったく違うのです。
◆なぜタイプが分かれるのか?
支援しづらく感じる方には、たいてい理由があります。
・人に頼らず生きてきた
・責任ある立場を経験してきた
・「弱みを見せない」ことが美学だった
・家族や地域での役割を長く担っていた
逆に、にこにこタイプの方は、
・人とのつながりが好き
・人に任せるのが上手
・ありがとうが習慣になっている
・もともと柔らかいコミュニケーションをしてきた
そうした人生背景が、そのまま認知症の段階になっても出てきます。
◆支援側ができること
大切なのは、タイプに応じた関わり方です。
✅ プライドの強い方には
・頭ごなしに否定しない
・頼るのではなく「お願い」という形にする
・役割を残す(例:確認だけお願いしますね 等)
・できている部分を認めてから声をかける
✅ にこにこタイプの方には
・感謝にはしっかり応える
・安心できるペースを守る
・できることを奪わない
・会話やスキンシップも大切に
支援のしやすさに差があるのは当然のこと。その違いを理解して関わるだけで、
こちらの負担感もぐっと変わってきます。
◆おわりに
認知症になると、その人の本質がより表に出ると言われます。
支援を拒まれるとき、私たちはつい「困ったな」と感じてしまいがちですが、
その裏には“その人らしさ”と“誇り”があります。
IさんもNさんも、どちらも長く地域で生きてこられた方。
その歴史を尊重しながら、「安心して頼ってもらえる支援者」でいることが、
私たちにできる一番の関わり方かもしれません。