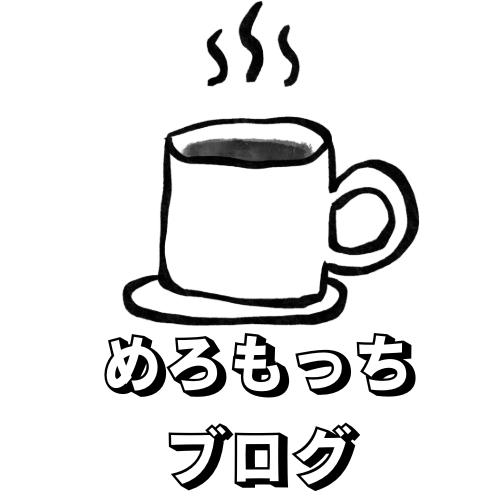「できるだけ自宅で過ごしたい」――そう願う高齢者は多いものです。
一方で、介護する家族や本人の体調の変化によって、
在宅生活を続けることが難しくなる場面もあります。
今回は、私が訪問介護で関わっている利用者さんの例も交えながら、
在宅介護から施設介護へ移る時期の目安について考えてみます。
在宅介護を続けられるケース
在宅生活が可能な場合には、次のような条件が整っていることが多いです。
-
本人が「自宅で暮らしたい」という強い希望を持っている
-
デイサービスや訪問介護などの支援サービスで日常生活が補えている
-
家族の協力が得られている
-
医療的処置が少なく、通院で対応できる
実際の利用者さんの例
私が訪問している一人暮らしの利用者さん(80代女性)は、数か月前に圧迫骨折をされ、
現在はコルセットを着けて生活されています。
-
週2回のデイサービス
-
週3回の訪問看護
-
週3回のヘルパー支援
を利用し、何とか自宅での生活を続けられています。
ただし、娘さんとはあまり関係が良くなく、必要な物を電話で頼む程度の
関わりにとどまっています。
ご本人は「施設に入ると自由がなくなるのではないか」
「もし嫌になっても、今の賃貸の家には帰れない」と不安を口にされます。
このように、身体的には在宅生活がギリギリ可能でも、
将来を見据えて施設を検討し始める方は少なくありません。
施設介護を検討すべきサイン
施設入所を前向きに考えるべきタイミングには、いくつかの共通点があります。
本人の変化
-
転倒や徘徊が増えて、自宅での生活が危険になってきた
-
夜間の介助が必要で、家族が休めなくなる
-
食事・排泄・入浴など、全面的な介助が必要になる
家族の変化
-
介護疲れによる体調不良が続く
-
仕事や生活への影響が大きくなる
-
介護に追われ、気持ちが追い詰められてしまう
医療面の変化
-
医師やケアマネジャーから施設入所を勧められる
-
医療的ケア(吸引や胃ろうなど)が必要になった
施設を検討するときのステップ
-
まずはケアマネジャーに相談し、情報を集める
-
ショートステイを利用して「施設生活」を体験してみる
-
家族で「ここまでなら在宅、それ以上は施設」とラインを話し合っておく
-
施設は入所待ちが発生することもあるため、早めの見学・申込みが安心
まとめ
在宅介護から施設介護への切り替えは、「自宅か施設か」という単純な選択ではなく、
本人が安心できるか、家族が無理なく支えられるかが大切な判断基準になります。
施設に入ることで自由が制限される面もありますが、その分「安全」「安心」
「専門的なケア」が得られます。
「施設に入る=見捨てる」ではなく、生活の質を守るための選択
だと考えていただければと思います。