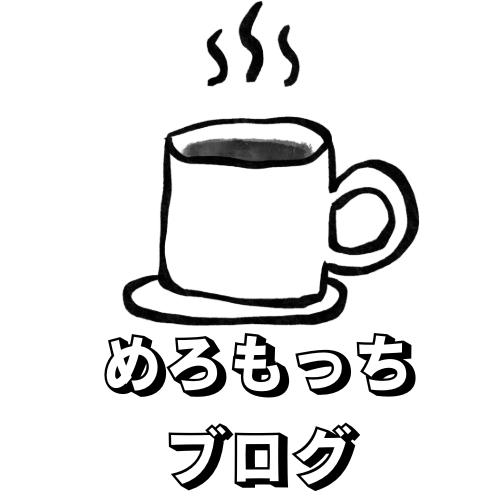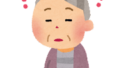徘徊により、行方不明になる高齢者は年々増加し、全国で1万8千人にも達しています。
認知症による徘徊は止めることが難しく、事件や交通事故に巻き込まれるリスクがあります。
思いついたら止められないKさん
Kさんはお上品な利用者さんで、お花やお茶をしていたせいか、所作がきれいです。
お茶を飲むときにも、両手で飲みますし、ご飯を食べる前にも手を合わせ、
薬を飲むときにも少しずつ飲んでくれます。
漢方薬を飲むときまで、少しずつ手に出して飲もうとするので、
そこは直接口に運んでいただいてます(笑)
いつもはのんびり過ごすKさんですが、急に思いついて立ち上がり、
何処かへ行こうとします。どこに行こうとするのかお聞きすると、
「郵便局に行かんと」「振込しないと」と言われます。元金融機関に
お勤めしていたらしく、お金の扱いが上手です。
そんな時は、「もう夕方ですから、お店しまってしまいました。
明日にしましょうか?」
とか、
「今はまだ暑いので、熱中症になったら大変!
もう少し涼しくなってからにしましょうか?」などと伝えると、
一旦納得してはくれるのですが、しばらくしてまた思いついて立ち上がります。
そうなると、職員は止められず、散歩に行くことになります。
しばらく歩くと、気が済むのか、疲れるのか、「そろそろ、帰りましょうか?」
というと、納得して帰ることになります。
徘徊するのは理由がある。
Kさんの口癖が「ごめんなさいね、迷惑ばかりかけて・・・」でした。
トイレ介助に行くときも、お風呂に入るときも
「私、おかしくなって何もできなくなったの。」とおっしゃってました。
自分でしなくちゃと思う反面、それができないのをストレスに感じていたようです。
それが不安につながって、居ても立っても居られなくなり、歩いてしまうことがあります。
また、昔の習慣を思い出すことにより、徘徊をしてしまうこともあります。
子供のお迎えの時間とか夕飯の準備のための買い物とか・・・
本人にとって、目的のために歩いてるのです。その途中で、思考力や判断力が失われ、
徘徊につながってしまうのです。
徘徊の対処法は?
一番ダメなことは、無理に止めることです。
理由があって行こうとするのにそれを止めるのは逆効果です。
Kさんの場合も、説得してなんとか座ってもらった場合、
ストレスが溜まって物にあたったり、暴言が出たりしたこともあります。
まずは、話を聞くこと。 怒らないこと。
実際にはなかなか難しいですが・・・ 話を聞いてもらったことで
納得する場合がほとんどです。
次に、一つの作業に集中させることです。
Kさんは金融関係の仕事をしていたので、100均のお札を仕分けしたり、
ノートを渡して書いてもらったりしていました。
時にはお茶を立ててもらってお茶会をしたり。
何かお手伝いを頼めば、自分にも役目があり、「自分の居場所」
を見つけて安心できるのではないでしょうか。