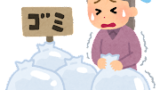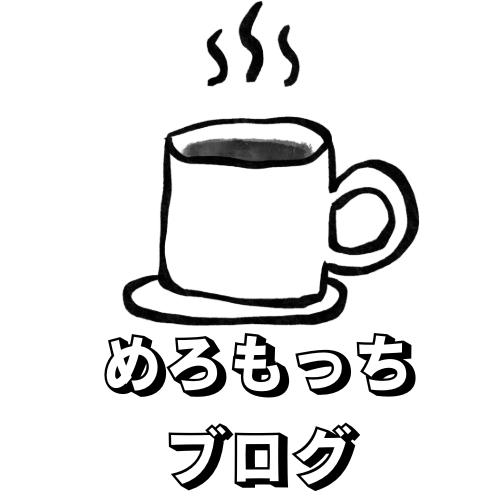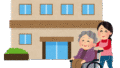訪問介護で伺うOさん。ゴミ出しをしていた時に段差に躓き、転倒。
骨折して入院することになりました。
手術・リハビリを終えて、自宅に戻ってきましたが、大きな問題として、
ゴミ問題があります。
訪問介護の現場でよく直面する課題のひとつに、「ゴミ出し問題」があります。
生活援助の一環として対応することもありますが、
制度や時間の制限によって、スムーズにいかないケースも多くあります。
早朝のゴミ出し時間とヘルパー訪問のズレ
多くの自治体では、可燃ごみの収集が朝8時前後と早い時間帯に設定されています。
しかし、訪問介護のサービス時間は、ケアプランにより10時〜や午後からなどに
固定されている場合が多く、ゴミ出しの時間と合わないのが現状です。
例えば、前記のOさんの場合も、外に出るのは危険な状態。
プラスチックなどの資源ごみは、ヘルパーが訪問する10時ごろにはまだ出せるのですが、
可燃ごみは早朝8時頃には収集車が来るそうで、
結果的にゴミが出せず、家の中にゴミが溜まってしまいます。
制度の壁:「要支援」では支援が受けられない現実
さらに問題なのが、自治体による「ふれあい収集」などのゴミ出し支援制度の多くが、
「要介護1以上」を対象としている点です。
そのため、要支援1・2の方は支援制度の対象外となり、
ゴミ出しに困っても公的支援を受けられません。
実際に困っている例:
- 軽度の認知症で外出に不安があるが「要支援1」
- 身体が不自由でゴミ出しが難しいが、要介護認定には至らない
このような方々が、制度の狭間に取り残されているのが現状です。
現場ではどう対応しているか
現場のヘルパーやケアマネジャーは、以下のような工夫をしながら対応しているようです。
- 前日にゴミをまとめて玄関に置いておいてもらう
- ゴミ出しの日に合わせてサービス時間を調整(できる範囲で)
- 本来業務外の時間に善意で対応(※これは制度的には望ましくない)
しかし、これらは“個人の努力”に頼る形になっており、根本的な解決策とは言えません。
解決のヒントと連携の必要性
このようなゴミ出し問題に対して、次のような取り組みや工夫が考えられます。
- ケアマネジャーと連携してケアプランの見直し
- 自治体の支援制度を確認・個別に相談
- 地域包括支援センターや民生委員との連携
- ゴミの一時保管に適した福祉用具の導入
特に「要支援」の方が困っている場合は、行政との橋渡し役として
ケアマネジャーの役割が重要です。
おわりに
「ゴミ出し」という、いわば“当たり前の生活の一部”が、
高齢者にとっては大きな壁になることがあります。
高齢者が安心して自宅で暮らし続けるには、こうした“日常の些細なこと”が
スムーズにできることが何より大切です。
制度やサービスのすき間を、どう埋めていくか。
現場に携わる者として、今後も声を上げ、地域や行政との連携を深めながら、
よりよい支援の形を模索していきたいと感じています。
ごみのふれあい収集についての関連記事は↓